Sony Acceleration Platformでは、大企業の事業開発を中心に、さまざまなプロジェクトを支援しています。本連載では、新しい商品や技術、サービスアイデアの事業化を行う会社や起業家など、現在進行形で新しい価値を創造している方々の活動をご紹介します。
今回は、ソニーのソフトウェア開発のテスト・品質保証の第一人者として長年先頭を走り続けてきた、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社の公文一博に、ソフトウェア開発の新しい品質保証ソリューション「EnQualitas」とその誕生背景について、お話を伺いました。
ソフトウェア開発の上流工程からバグを未然に防ぎ、大幅なコストカットを実現できる世界とは―。
本記事に関連して、10月23日(木)に『ソフトウェア品質は「上流で作り込む」時代へ。ソニー式「EnQualitas」の実践』と題した無料セミナーを開催します。ご興味をお持ちの方は、以下より詳細をご確認の上、お申し込みください。
>> セミナーの詳細・お申し込みはこちら
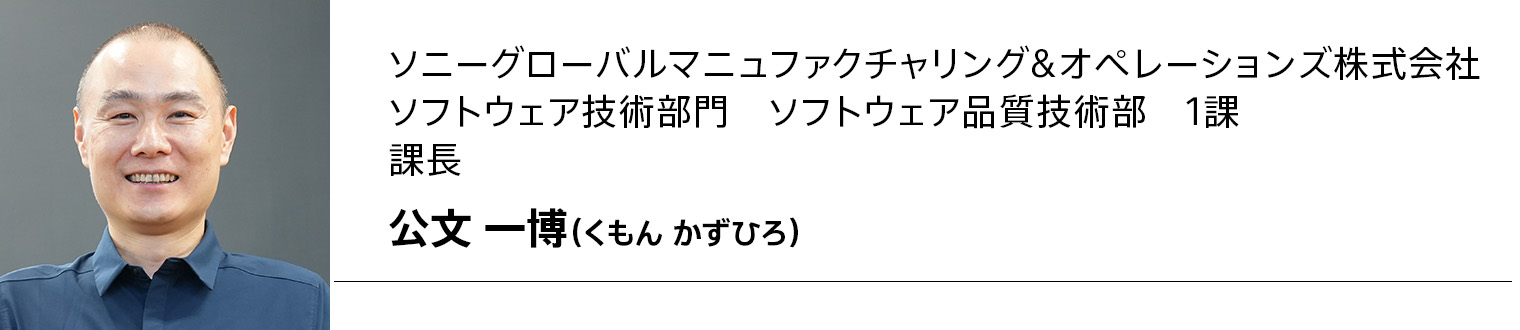
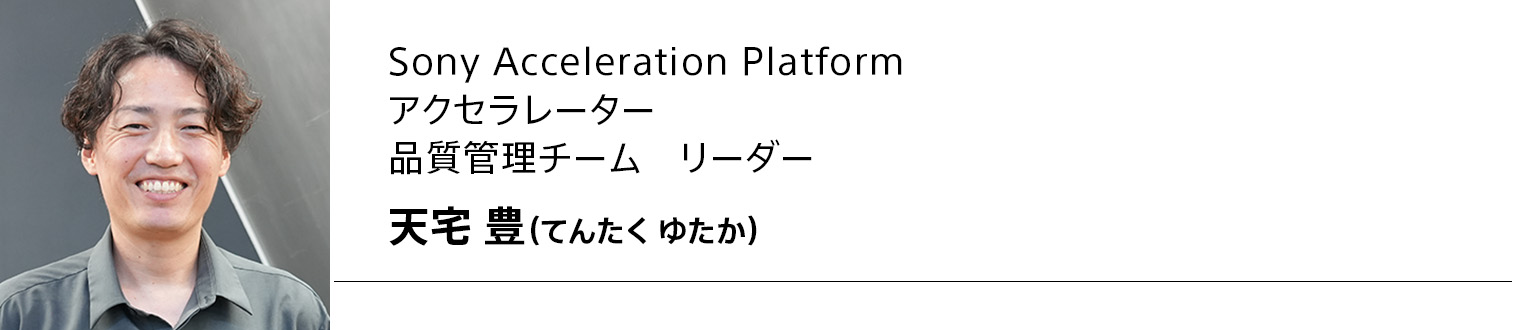

キャリアが導いた発見 - 1万時間に迫るバグ分析で見つけた「パターン」
――品質改善ソリューション「EnQualitas」のリリースにあたり、ソリューションの構想に至るまでの背景を教えてください。
公文:私はソニーに入社後、デジタルイメージング領域、ビデオカメラなどのソフトウェア開発者としてキャリアをスタートさせました。最初の仕事は、ソフトウェアの仕様を書いたり、カメラを動かすための固有のシステムを制御したりするような、まさに開発の根幹に関わる部分でした。
しばらくして組織内で「ソフトウェアのテスト専門チームを作ろう」「開発プロセス自体を改善していこう」という動きが起こり、私もそのチームへ異動することになりました。それが、私がソフトウェアテストと品質保証の世界に深く足を踏み入れるきっかけでした。
正直、最初は手探りの状態でした。