Sony Acceleration Platformでは、大企業の事業開発を中心に、さまざまなプロジェクトを支援しています。本連載では、新しい商品や技術、サービスアイデアの事業化を行う会社や起業家など、現在進行形で新しい価値を創造している方々の活動をご紹介します。
今回は、常陽銀行の新規事業開発プログラムの立ち上げと運営に携わるお二人と、その支援パートナーであるSony Acceleration Platformの担当者に新規事業開発プログラムの立ち上げの背景や運営課題の解決から、参加者にもたらされた変化まであらゆる観点でお話を伺いました。
行員全員が新規事業に挑戦できるような企業風土の醸成とは―。常陽銀行の挑戦のリアルに迫ります。
>> 2記事目:株式会社常陽銀行 #02|行員のアイデアが地域の未来を拓く。顧客基盤を活かした共創型ビジネスの可能性
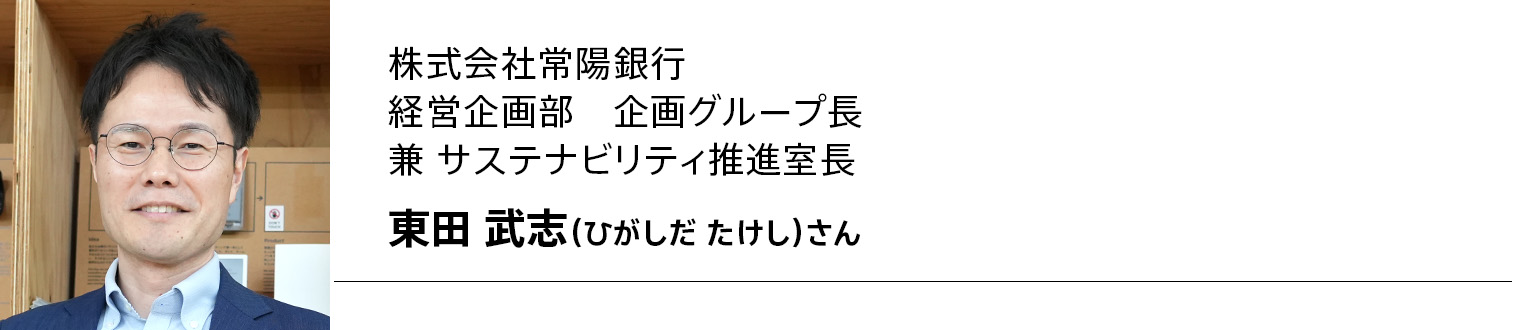
めぶきフィナンシャルグループ(FG)および常陽銀行の経営企画部に所属。茨城県内での個人・法人営業、東京都内での法人営業を経験後、経営企画部において中期経営計画の策定や組織設計、グループ会社の経営管理を担当した他、足利銀行との経営統合の際には、統合プロジェクトチームの一員として統合準備および統合後のPMIに携わる。現在、FGにおいてはグループ戦略やサステナビリティ戦略の立案を担当。常陽銀行においては、CVCや戦略的な提携・出資の活用、インキュベーションプログラムの運営などによる新規事業開発を行うチームのリーダーを担う。
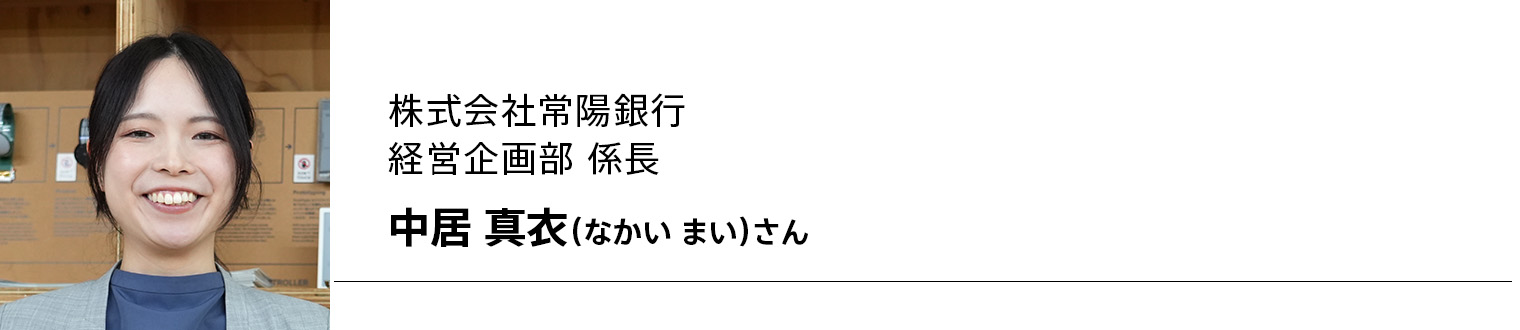
めぶきFGおよび常陽銀行の経営企画部に所属。入行から5年間、支店で法人営業や融資業務、預かり資産などの業務を担当。トレーニー制度を活用し、本部DX部門でのトレーニー経験で行内のDX企画などに携わったのち、経営企画部に転籍し4年ほど従事。現在は、主にインキュベーションプログラムの企画運営、またCVC活動のソーシングなど、新規事業の開発の業務に携わる。
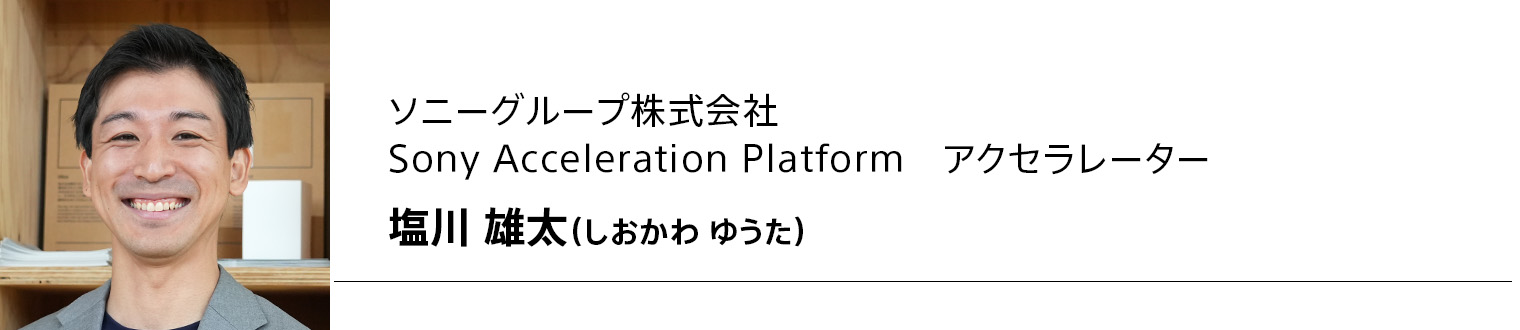
通信事業会社およびコンサルティングファームを経て、ソニーグループ株式会社に入社。コンサルティングファームではDX戦略の策定・実行支援、組織変革プログラムの推進など、企業のデジタルトランスフォーメーション実現に貢献。現在はSony Acceleration Platformのアクセラレーターとして、業種を問わず多様な企業の新規事業に関する企画立案や制度設計、ビジネスコンテストの企画・運営支援、事業開発に関するトレーニングやメンタリングに従事。

はじめに
――常陽銀行さんの事業概要や地域との関わりについて、教えてください。
東田さん:めぶきフィナンシャルグループの常陽銀行は、茨城県を地盤とする地方銀行で、創立以来90年にわたり地域とともに歩み幅広い金融サービスを提供しています現在はめぶきフィナンシャルグループとして、足利銀行と経営統合しています。
地方銀行ですので、基本的には地域の活性化に資するようなビジネスを展開していますが、営業エリアは福島県や栃木県、千葉県にも及んでおり、地方銀行の中では顧客エリアが広い部類に入ると思います。
銀行業務がビジネスのほとんどを占めていますが、それだけでは地域の課題解決は難しいのが現状です。金融ビジネスだけでなく、新たな事業領域を確立することで地域課題の解決に貢献していくことが、我々のミッションだと考えています。

プログラム立ち上げのきっかけと当時の課題感
――今回のインキュベーションプログラムを立ち上げたきっかけを教えてください。
東田さん:プログラム立ち上げのきっかけは、2022年4月にスタートした当行およびめぶきフィナンシャルグループのグループ中期経営計画です。その中で掲げる、2030年に目指す姿である長期ビジョン「地域とともにあゆむ価値創造グループ」です。この長期ビジョンでは「価値創造」を大きなテーマとしており、地域のお客様のために新しい価値を創り続けるべく、事業領域の拡大を図るものとしています。
実際に、事業領域拡大の具体的な取り組みとして、再生可能エネルギー子会社「常陽グリーンエナジー」の設立(2022年7月)や、スタートアップ協創プログラム(2023年・2024年)などを実施してきました。
これらと並行して行う取り組みの一環として、2023年度より、従業員参加型の新規事業開発プログラム「常陽インキュベーションプログラム」をスタートしました。
2025年4月以降のグループ中期経営計画では、基本戦略の一つである社会課題解決戦略において、新規事業領域を「創造に挑戦する領域」と位置付けています。地域には少子高齢化、人口減少、環境問題などの様々な社会課題がありますが、これらの課題を放置してしまうと、地域経済の縮小につながり、それは私たちのビジネス機会の縮小につながるというネガティブな循環になってしまう恐れがあります。
新規事業領域への挑戦を通じ、さまざまな社会課題の解決にビジネスで貢献し、地域経済を活性化させ、私たちのビジネスも成長させ、地域のサステナビリティに貢献していくというポジティブな循環にしていくことが大きな狙いです。
――当時は、新しい事業に挑戦したいという方は行内にいらっしゃったのでしょうか。
東田さん:新規事業開発を担うグループはあったのですが、限られたメンバーだけで活動しているという印象が強く、なかなか新しいことが始まらないという課題がありました。
やはり、多くの行員の課題感や経験から新しい事業は生まれるものですから、特定のメンバーだけがやるのではなく、組織全体を巻き込む必要があると考えました。
お客様自身も多くの課題を抱えている中で、お客様と一緒になって新しいことを考えられる行員が必要だと感じました。組織的に新しいことに挑戦する風土を醸成したい、という思いからインキュベーションプログラムを実施しています。

――そのような課題の中で、どのようにしてSony Acceleration Platformと出会ったのでしょうか。
東田さん:正直に言うと、課題だらけで、社内には新規事業開発のノウハウも経験も全くない状態でした。どこかの支援を受けなければ難しいと考えていたところ、本当にたまたま、チームの者が受け取ったDMがきっかけでした。普段ならダイレクトメールをきっかけに話を聞く機会がなかなか無いのですが、それくらい困っていたんです。
実際にお話を伺うと、我々の要望やリクエストに柔軟に対応していただけそうな印象を受けました。地方銀行の支援はやったことがないとのことでしたが、逆にだからこそ、我々の状況に合わせて支援していただけるのではないかと期待しました。そこからトントン拍子に話が進み、最初は研修をお願いすることになりました。
具体的には、インキュベーションプログラムの前身として、2022年1月に「事業開発事業領域拡大に向けた研修プログラム」を開催しました。当行従業員のほとんどは、普段、支店で銀行業務(店頭、法人、預かり資産営業)に従事する方、本部で金融商品などの企画をしている方々であり、まずは「事業領域拡大の必要性」「新規事業とは何か」というところの説明などを通じ、事業開発は限られたメンバーの取り組みではなく、幅広い層に「組織的に取り組む」という意識を浸透させることが必要でした。
塩川:最初にご相談いただいた際は、全社からアイデアを募って事業化まで進めたいというご要望でした。しかし、お話を進める中で、普段の業務の忙しさから、そもそも「新しいことにチャレンジするための時間を持てない」という従業員が多い点も課題であり、まずは新規事業開発を通じて「従業員が新しいことにチャレンジできるような組織風土」の醸成や、そういった人材の育成が先だということになり、新規事業の取り組みのモチベーション向上にむけたセミナーや、新規事業開発の基本的な部分を学ぶ短期研修の開催などの研修プログラムから着手しました。
――研修プログラムを実施してみて、反響はいかがでしたか。
塩川:研修の参加者を募る際、常陽銀行様の行内にどれくらい事業開発に意欲のある方がいらっしゃるか、正直読めない部分がありました。当初、参加者は20名ほどを想定していましたが、蓋を開けてみれば倍以上の約50名から手が挙がったんです。これだけ「(新規事業を)やりたい」と思っている方がいるんだと、すごい驚きでしたね。
東田さん:私も、銀行員は新しいことをやりたがらないのではないかと勝手に思っていましたが、そうではないと分かり、良い意味で驚きました。
中居さん:研修を終えた参加者からは、「勉強になった」「自分の考えを整理してプレゼンする機会は貴重で、非常に良い経験になった」という声が多く聞かれました。また、「研修だけで終わりにするのはもったいない」という声が上がってきたのも、すごく良い流れでしたね。

ビジネスコンテストの実現と事務局の挑戦
――研修の成功を経て、ビジネスコンテスト「インキュベーションプログラム」の立ち上げに至ったのですね。立ち上げにあたってのご苦労はありましたか。
中居さん:私自身が2022年度の研修を受けた経験から、参加者が業務時間内にアイデアを練り、プレゼンまで準備する時間がいかに大変かを実感していました。ですから、事務局として、プログラムのスケジュールや回数が本当に適切なのかは常に悩みましたし、今でも試行錯誤しています。
東田さん:プログラム全体の設計は塩川さんにもご支援いただき、比較的スムーズに進められましたが、やはり応募いただいたアイデアの選定は毎回難しいですね。我々自身も事業開発の経験が豊富なわけではないので、一定の評価基準は設けつつも、どのアイデアを選ぶべきか、特に最初は手探り状態でした。ソニーさん側の審査結果と全然違ったらどうしよう、とドキドキしていました。
塩川:プログラム設計がスムーズに進んだのは、参加者としての経験を持つ中居さんが事務局にいたことが非常に大きかったと思います。参加者の肌感覚や工数感が分かっている方がいることで、カリキュラムのカスタマイズが的確にできました。企業によって投入できる工数や社員のベーススキルは大きく異なるため、画一的なプログラムでは効果を発揮できません。そのような状況下で、かつて参加者として経験を持つ中居さんが事務局メンバーとして加わっていただいたことで、プログラム設計を実態に即して進めることができました。参加者の実感や必要な時間感覚を理解している方がいることで、常陽銀行様にとって現場の視点に立ったカリキュラムへのカスタマイズが的確にできました。

――事務局の体制はどのようになっているのでしょうか?
東田さん:スタート時は私と中居の2名で、そこに塩川さんにサポートしていただく形で進めました。途中からもう1名メンバーが増え、現在は3名体制です。とは言え、私も色々兼務しているので、実質的には中居さんに任せている部分が多く、苦労をかけているなと感じています。
塩川:私は事務局の全体的なサポートや、トレーニングの講師、通過者への1on1メンタリングなどを担当させていただきました。
――具体的にどのようなプログラムで実施したのでしょうか。
中居さん:プログラムは大きく「研修フェーズ」と「アイデア公募フェーズ」に分けて実施します。研修フェーズについては希望者を対象にアイデア発想に関するワークショップの開催や研修動画の配信を行い、アイデア公募・選定フェーズについては、アイデアの公募を7月中旬に開始し、書類審査を行ったのち、通過者向け研修と最終審査を行いました。
詳細は以下の通りです。
<フェーズⅠ: 研修フェーズ>
1. マインド醸成セミナー(7月頃):事業開発に関するモチベーション向上を狙ったガイダンス形式のセミナー
2. アイデア創出ワークショップ「アイデアソン」(8月頃):グループワークで新規事業アイデアの発想を実施。めぶきFGとして開催し、めぶきFG内子会社の足利銀行からも参加。
3. ビジネスモデル構築トレーニングⅠ(9月頃): 事業開発の基礎やビジネスモデル構築方法のトレーニング(アイデア創出手法と価値顧客の検証シート)。2日間で実施。
<フェーズⅡ: アイデア公募・選定フェーズ>
1. 新規事業アイデアの公募(9月~10月頃)
2. 一次選考(2023年10月頃):応募アイデアを書類審査し、約10アイデアを選定。
3. トレーニングⅡ&メンタリング(11月~翌1月頃):一次選考通過者向けに研修・個別メンタリングを実施。ビジネスモデル仮説構築に関するトレーニングを計3日間行い、最終選考へ向けアイデアをブラッシュアップ。
4. 二次選考(2024年3月):役員向けプレゼンを実施、選考。事業化可能なアイデアについては翌年度以降に実証実験等を検討。

参加者に芽生えた変化とプログラムがもたらした価値
――プログラムを通じて、参加者に印象的な変化やエピソードはありましたか。
中居さん:お客様から直接聞いた課題を基にアイデアを応募された方は、最後まで粘り強く頑張っていた印象があります。また、事務局としては、参加者に対して的確なアドバイスが難しい中、情報提供などの支援は惜しまない姿勢でいました。当初は遠慮がちだった参加者も、次第に事務局を積極的に活用してくれるようになり、通過者にはそうした方が多かったですね。行員の意識が変わり始めているのを感じました。
東田さん:普段からお客様と真摯に向き合っている方は、やはり経験が強く活かされていましたね。プログラムの課題のひとつであるお客様へのヒアリングも、普段からの関係性があるためクリアしやすい。こうした動きが見えてくるのは、運営側として非常に嬉しいです。
また、周囲を巻き込むのが上手な方も、アイデアが良く、最後までやり遂げられる傾向にありました。「応援してくれた部のみんなに見せたい」と部署内のメンバーに配信を通してプレゼン発表会を見せていた参加者もいて、チームで取り組む文化が生まれているのを感じます。
塩川:皆さん、日常業務を抱える中でも非常に熱心にプログラムに取り組まれていたという印象を強く持ちました。私どもが様々な企業様を支援する中では、多くの障壁にぶつかり途中で離脱してしまう参加者が一定数出るのが通常です。しかし、常陽銀行様においては参加者全員が最後までやり抜き、最終プレゼンまで完遂されています。これ自体も非常に価値ある成果だと考えています。この成功の背景には、プログラムの核心部分である「お客様へのインタビューを通じた仮説検証プロセス」において、事務局の皆さんが参加者がインタビューのアポ取りを積極的に支援するなど、きめ細やかなサポートを提供されていたことが大きく貢献していると思います。
中居さん:若手の参加者など、お客様との接点がまだ少ない行員もいます。そうした参加者のために、インタビュー先の紹介など、事務局が持つ人脈を活かしたフォローは意識して行っています。私たちがフォローすることで、参加者はアイデアを考えることに集中できますから。
東田さん:嬉しかったエピソードとしては、新入社員のアイデアで顧客ヒアリングに同行した際のことです。彼の考えた解決策は刺さらなかったのですが、お客様から「銀行が我々の課題を本気で考えて、何とかしようとしてくれる、その姿勢が嬉しい」と言っていただけたんです。我々の取り組みが、お客様に価値として感じていただけた瞬間でした。
中居さん:現在では「インキュベーションプログラム」として連続開催し、他部店の方から、開催前にもかかわらず「今年も応募するよ」などお声がけいただくなどの反響いただくようになりました。今後も、当行が事業領域の拡大に取り組んでいることを周知しつつ、より多くの従業員に参加してもらえるようなプログラムにしたいと思っています。

新規事業にこれから挑戦する皆さんへのメッセージ
――最後に、これから新規事業に挑戦しようと考えている方々へメッセージをお願いします。
中居さん:新規事業開発は「千三つ」と言われる世界で、1000のアイデアのうち事業化するのは3つ程度です。ですから、自分のアイデアが事業化しなくても、そこがゴールではありません。プログラムで学んだこと、経験したことは、お客様とのコミュニケーションや今後のキャリアに必ずプラスになります。私たちにとっては、お客様の課題を見つけ解決策を考えるプロセスは、銀行員の仕事そのものです。
挑戦すること自体に大きな価値があるので、業種・職種に関わらず、ぜひ新規事業開発やそれに通づる企業内外のプログラムなどへの挑戦の一歩を踏み出してほしいです。
東田さん:新規事業開発という言葉にはまだ特別感があるかもしれませんが、この取り組みは、多様な視点で物事を考える絶好の機会です。さまざまな視点で物事を繰り返し考える、新しい視点で物事を組み立てていくという訓練は、仕事だけでなくプライベートを豊かにするきっかけにもなります。得られるものは非常に多く、「やらなきゃ損」だと思っていますので、ぜひ多くの方にチャレンジしていただきたいです。
中居さん:銀行にはメーカーのような明確な技術はありません。だからこそ、お客様との接点や、行員一人ひとりが持つ「人の力」が最大の武器になります。自分の経験がどう活かせるか分からないと思っている方でも、ぜひ挑戦してほしいと思います。
東田さん:まさにその通りで、銀行は人が資本のサービス業です。お客様と一緒に課題を考え、解決していく。この取り組みは、我々が提供できるサービスの根幹であり、非常に重要な活動だと考えています。


いかがでしたか?ビジネスコンテストの事務局の皆さんの応募者の皆さんと真摯に向き合う姿勢や、応募者の皆さんの真剣さが伝わってきました。
次回は、常陽銀行内で実際にビジネスコンテストに参加、審査を通過して事業化を成し遂げた担当の方のインタビューをお届けします!