Sony Acceleration Platformでは、大企業の事業開発を中心に、さまざまなプロジェクトを支援しています。本連載では、新しい商品や技術、サービスアイデアの事業化を行う会社や起業家など、現在進行形で新しい価値を創造している方々の活動をご紹介します。
今回は、AIとIoTによって「現場の仕事をラクにする」ことに挑むLiLz株式会社(以下、リルズ)です。
技術革新によって、あらゆる社会課題に革新的なアプローチが可能になってきましたが、設備保全や建設、農業、漁業などの現場の仕事では、一般的なIT技術では解決が難しい複雑な課題がまだ多く残されています。
そうした課題に対して、リルズはどのように解決していくのか。同社の代表取締役社長である大西敬吾さんに、起業の経緯や直面した壁、そして業界初となる防爆対応IoTカメラ「LC-EX10」の開発秘話について詳しく伺いました。
後編では、さまざまな困難が立ちはだかった防爆認証の高い壁をどのように乗り越えたのかご紹介します。(前編はこちら)
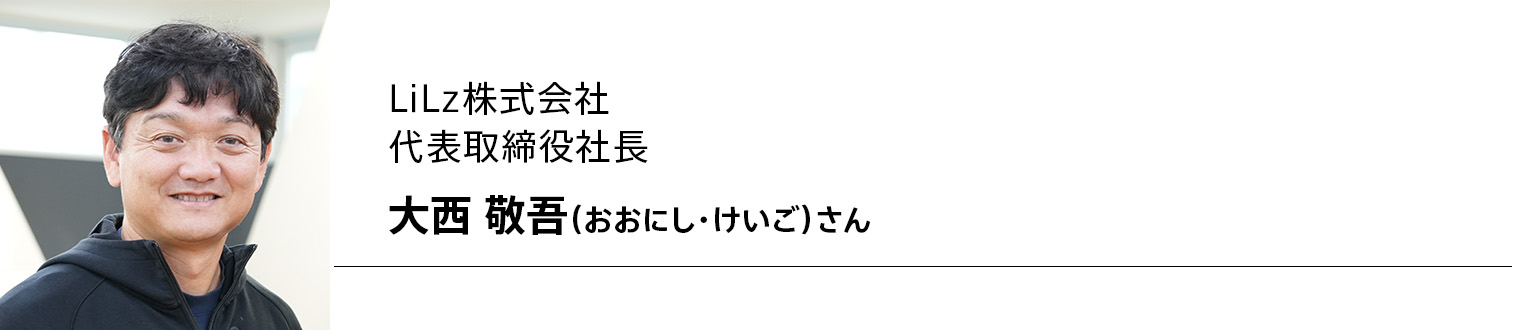


■防爆対応の高いハードルとSony Acceleration Platformの支援
―― 防爆対応のIoTカメラ「LC-EX10」を開発する上で、どのような難しさがありましたか?