Sony Acceleration Platformでは、大企業の事業開発を中心に、さまざまなプロジェクトを支援しています。本連載では、新しい商品や技術、サービスアイデアの事業化を行う会社や起業家など、現在進行形で新しい価値を創造している方々の活動をご紹介します。
今回は、システムインテグレーターのネットワンシステムズ株式会社(以下、ネットワンシステムズ)の皆様に、生成AIを業務に導入した背景や、それによって生まれた変化についてお話しを伺いました。
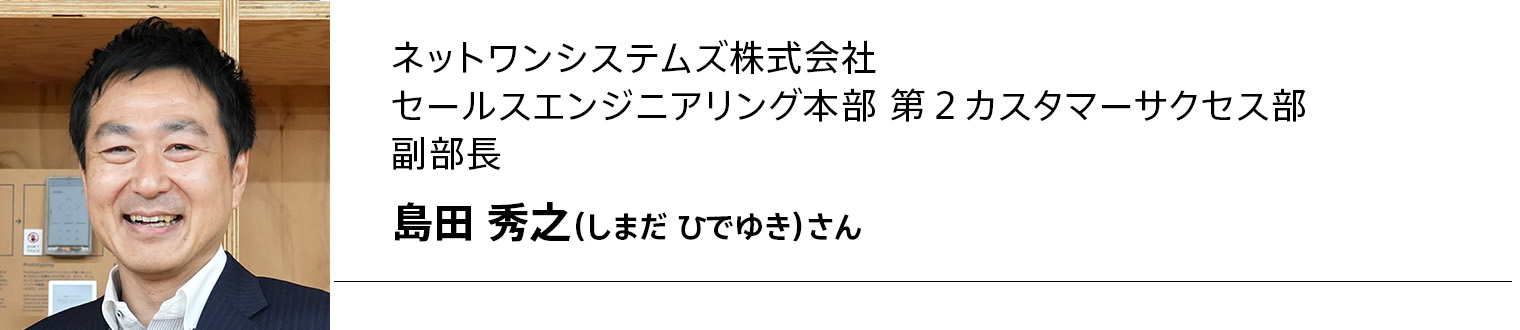
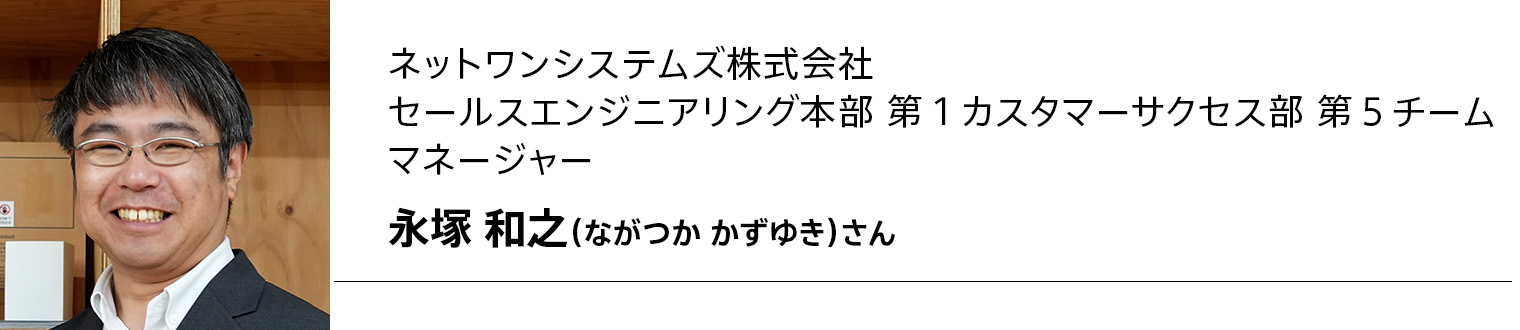
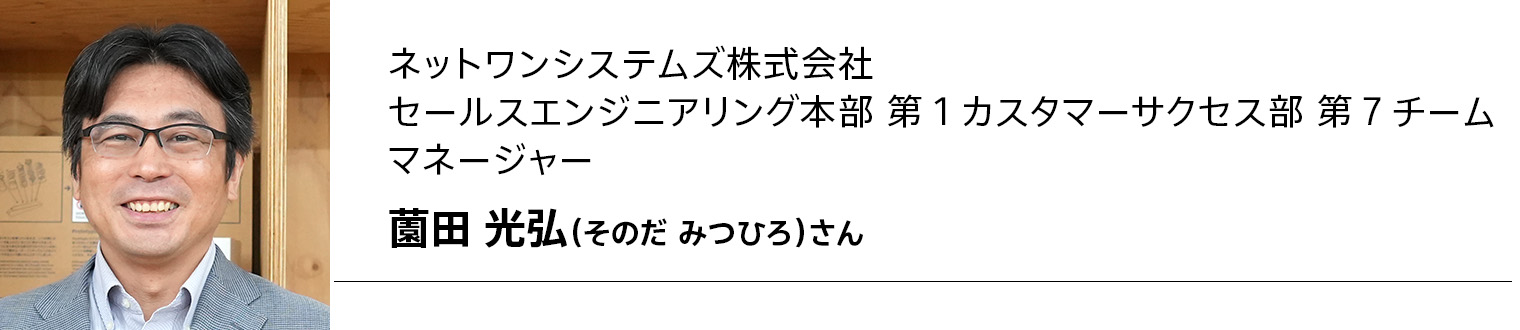
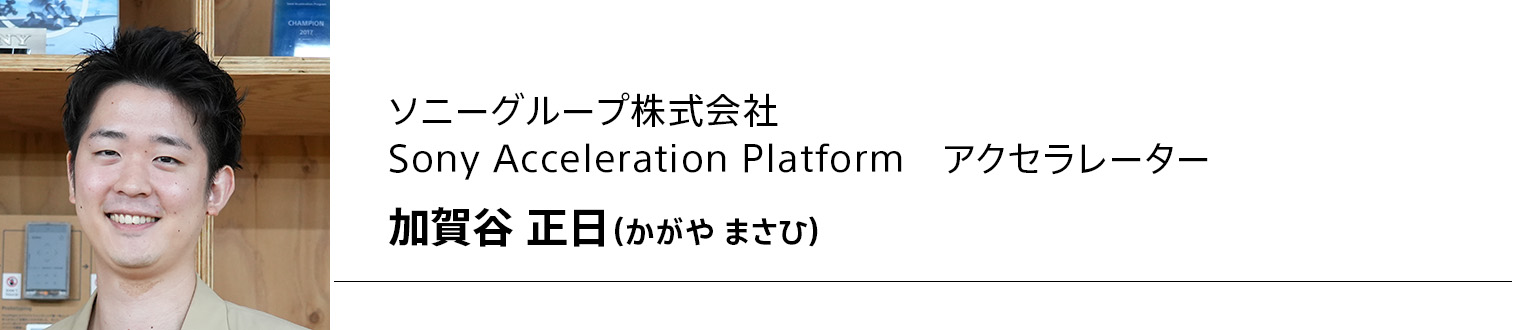

はじめに
――ネットワンシステムズ社の事業概要と、皆様が所属されているカスタマーサクセス部の役割について教えてください。
島田さん:私たちネットワンシステムズは、創業当時はネットワーク事業を強みとしていましたが、現在ではネットワークだけでなくサーバーや各種メーカー製品、そして自社のサービスを組み合わせ、お客様に総合的な情報インフラ構築とそれらに関連したサービスを提供しています。
企業理念には「人とネットワークの持つ可能性を解き放ち、伝統と革新で豊かな未来を創る」と掲げています。これは、私たちが長年培ってきた匠の技術、いわば「伝統」と、AIのような新しいテクノロジーという「革新」を融合させ、お客様と共に未来を創造していく「共創ビジネス」を目指すという意思の表れです。
私たちの所属するセールスエンジニアリング本部は、コンサルティングから、運用、セキュリティ、ファシリティ、プロジェクトマネジメントまで、あらゆるサービスを集約した組織です。その中で、私たち第1・第2カスタマーサクセス部は、主にお客様先でのシステム運用サービスを担う部門です。
第1カスタマーサクセス部は製造業などのエンタープライズ系企業を主に担当し、提案活動を支援する専門部隊なども擁しています。一方、第2カスタマーサクセス部は公共系のマーケットに加え、北海道から西日本まで全国のエリアをカバーしています。 お客様の業務運用をアウトソーシングという形で支援し、お客様が本来のコア業務に集中できるよう、IT運用の側面からビジネスを成功に導くことが私たちのミッションです。

「顧客満足度向上」の裏にあった、運用現場の根深い課題
――お客様のビジネスを深く支援する業務の中で、生成AIの導入を考えるきっかけとなった具体的な課題は何だったのでしょうか。
薗田さん:やはり、運用現場の管理者の業務負荷の増大が深刻でした。