ソニーグループ株式会社が手掛ける、デジタルツイン開発プラットフォーム『Mapray』。構想から10年を経て、いよいよ本格的な事業展開の段階となりました。そこで、企画・開発者の皆さんに、10年の軌跡と新たな挑戦について、お話を伺いました。
なお、10月14日(火)~17日(金)に千葉県の幕張メッセで開催された「CEATEC 2025」にSony Acceleration Platformが出展する展示ブースにて、Maprayプロジェクトもご紹介いたしました。


坂元 一郎
ソニーグループ株式会社 デジタル&テクノロジープラットフォーム アドバンストテクノロジー システムプラットフォーム技術部門 デジタルツインシステム開発部
シニアソフトウェアマネージャー
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)に入社後、オーディオ、ビデオ、テレビ、ゲーム機といった製品でのソフトウェア開発を経験。その後、新規事業にてクラウドサービス開発に携わり、現在はR&D部門でMaprayを起点としたデジタルツイン技術の開発マネジメントを担当。モビリティ事業部門と連携しながら、事業創出に取り組んでいる。

松本 大佑
ソニーグループ株式会社 デジタル&テクノロジープラットフォーム アドバンストテクノロジー システムプラットフォーム技術部門 デジタルツインシステム開発部 兼 モビリティ事業部門 モビリティーサービス開発部
シニアソフトウェアエンジニア
3DCG技術を専門とするスタートアップに入社し、ソフトウェアエンジニアとして数々のプロジェクトに参画。3Dレンダリングエンジン事業をゼロから立ち上げ、大手自動車メーカーなどに採用される。ソニー(現ソニーグループ株式会社)に入社後は、組み込み向けWebプラットフォームの開発を担当。ゲーム機をはじめとするソニー製品に広く採用される。社内制度を活用して新規事業創出部門に異動し、GIS技術を用いたクラウドサービスを立ち上げ、 開発責任者としてエアロセンス株式会社の初期メンバーとして参画。その後、Maprayプロジェクトを立ち上げ、現在はR&D部門に所属。

佐藤 一喜
ソニーグループ株式会社 モビリティ事業部門 モビリティサービス開発部 サービス企画課
大手自動車会社、人材会社を経て、ソニーグループ株式会社に中途入社。自グループの技術調査・戦略策定などを担当し、現在は、新規事業創出に取り組んでいる。

武藤 陸
ソニーグループ株式会社 モビリティ事業部門 ビジネスディベロップメント部 1課
新卒でソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)に入社後、広報に配属。プロダクトやテクノロジー、新規事業などの領域におけるPR・メディアリレーションを担当し、2024年に社内制度を活用しモビリティ事業部門へ異動。

デジタルツイン開発プラットフォーム「Mapray」
――はじめに、Maprayの概要を教えてください。
坂元:Mapray(マップレイ)は、3Dデータと様々な情報を集約して高度なデータ活用を可能にする、オープンなデジタルツイン開発プラットフォームです。開発者はMaprayを利用することで様々なデジタルツインサービスの開発が可能になります。
開発体制としては、プロジェクトオーナー、プロジェクトマネージャーの下に、企画担当である佐藤・武藤と、技術担当として松本と私が所属する組織のエンジニアがいます。新規事業のため少数精精鋭ではありますが、チーム一丸となって事業化を進めています。
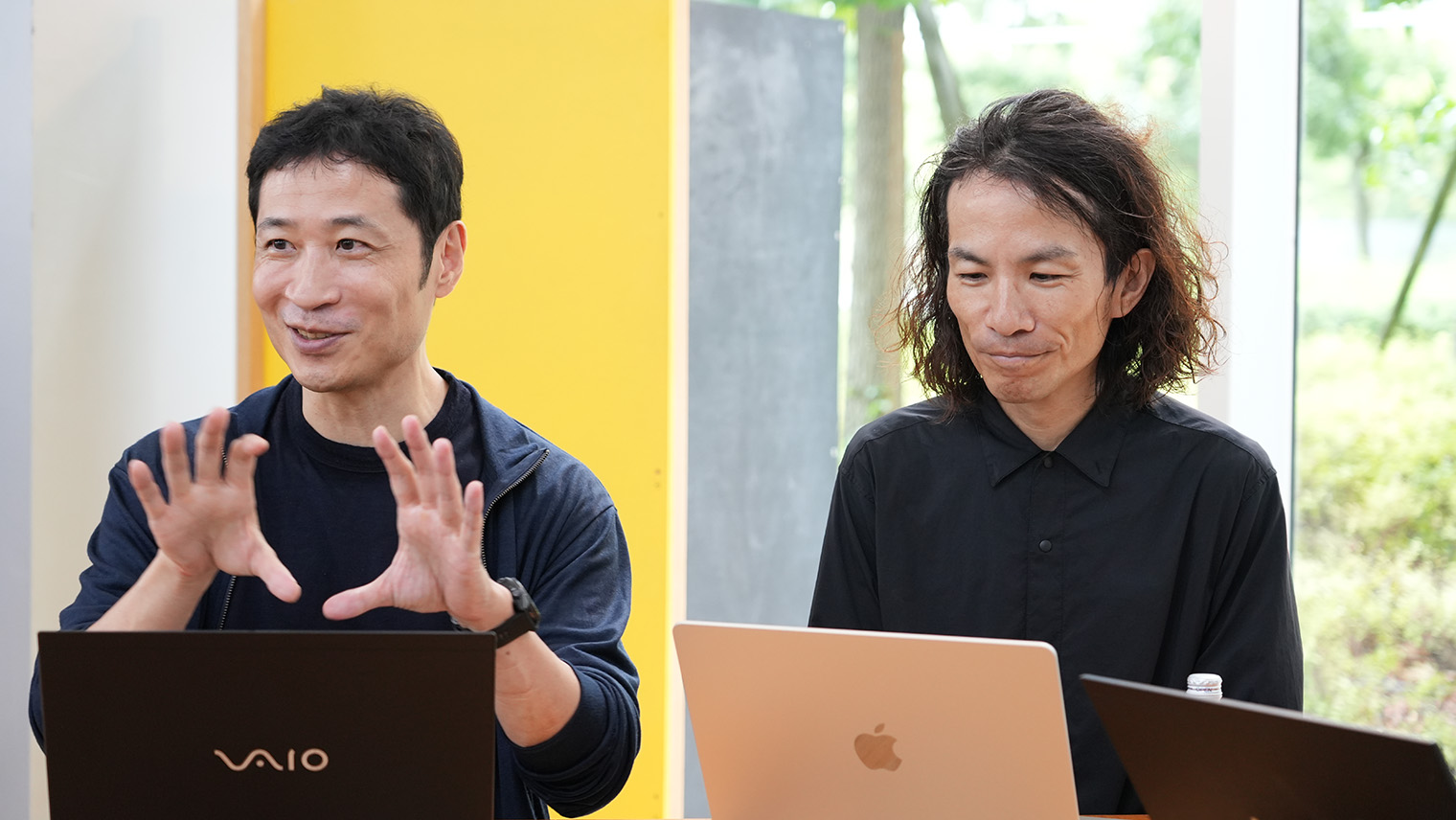
はじまりは10年前のサンフランシスコ
――プロジェクトは、いつ頃、どのような経緯で始まったのでしょうか。
松本:話すと長くなるのですが(笑)、最初のきっかけは2015年に遡ります。 当時、私は新規事業を立ち上げる部署に異動し、サンフランシスコで開かれた「GitHub Universe」というカンファレンスに参加する機会を得ました。そこで初めて「オープンデータ」という概念を知ったのです。当時米国では既に大統領令で、国が取得したデータを原則公開しなければならないと定められていました。そのベース技術がオープンソースで、代表例としてGIS(地理情報システム)のソフトウェアが非常に多く使われていたのです。
それまで地図ビジネスといえばGoogle マップで勝負はついていると考えていたのですが、BtoBの世界では全く違うものが使われているとわかり、帰国後すぐに研究開発を始めました。当時はドローンが流行り始めた頃で、ドローンで空撮した写真から世界を3Dでキャプチャーできる技術に衝撃を受けました。 GISの世界では3Dグラフィックス技術との『融合』が始まっており、これまでの地図の常識を覆すような、新たな次元の表現が可能になりつつあることを感じました。グラフィックスをやってきた人間として、「こんなことがドローンでできてしまうのか―。あっという間に地球上のデータが取れてしまう、これはすごいビジネスになるぞ…!」と。